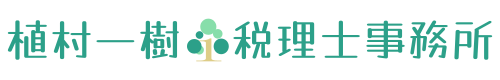不動産所得や事業所得がある方で、「青色申告承認申請書」を提出している方は、青色申告特別控除を受けることができます。
受けることができる控除額は要件により異なりますので、内容を確認してみましょう。
青色申告特別控除額の種類と要件
青色申告特別控除額には、
- 65万円
- 55万円
- 10万円
の3種類があります。
このうち、65万円、または55万円の控除を受けるには要件があり、要件を満たさない青色申告者は10万円の控除となります。
65万円の青色申告特別控除を受ける要件は次の通りです。
- 事業的規模の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む者であること
- 正規の簿記の原則(複式簿記)に従って取引を記録していること
- 貸借対照表、損益計算書を作成し、確定申告書に添付していること
- 申告期限内に申告書を提出すること
- 青色申告者のうち、現金主義による所得計算を選択していないこと
- 次のいずれかを満たすこと
・その年分の確定申告を期限内にe-taxで行なっている
・その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳につき、電子帳簿保存法の規定に従って電磁的記録の備付け及び保存を行なっている
上記のうち6.のみ満たしていない場合には、控除額が55万円となります。
そして、1~5のいずれか1つでも満たしていない場合には、控除額が10万円となります。
65万円の控除を受けるには?
では、65万円の控除を受けるには何をすればよいのでしょうか。
要件を紐解いてみます。
「事業的規模の不動産所得」又は「事業所得」を生ずべき事業を営む者であること
「事業所得」がある方は問題なく要件を満たします。
一方「事業的規模の不動産所得」は、原則として“社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか”により判定します。
はい、余りにも曖昧ですよね。
そこで、形式的に次に該当する場合には要件を満たすこととしています。
【形式基準(5棟10室基準)】
■建物
・貸間、アパート等の独立した室数がおおむね10室以上。
・独立した家屋の貸家数がおおむね5棟以上。
■土地
・土地、駐車場の契約件数がおおむね50件以上(貸室1室=土地5件として判定する)
正規の簿記の原則(複式簿記)に従って取引を記録していること
貸借対照表、損益計算書を作成し、確定申告書に添付していること
損益の集計(損益計算書)だけでなく、資産と負債の状態(貸借対照表)もまとめることが必要です。
この要件を満たすにあたっては、会計ソフトを使用することが最も負担が少ないです。
会計ソフトを使用しての会計処理は必然的に複式簿記での記帳となります。
(ちなみに、家計簿のように収入や経費をその項目ごとに集計しただけのものが単式簿記です。)
そして、複式簿記で記帳することにより、損益計算書だけでなく、貸借対照表も合わせて作成されることになります。
ただし、“正規の簿記の原則”と銘打っている通り、ただただ会計ソフトへ取り込むor入力するだけではダメで、簿記のルールに則って会計処理を行う必要があります。
損益の集計にのみ意識が集中してしまい、貸借対照表の残高が根拠のないとんでも数字になっている、というのでは、正規の簿記の原則に従っているとは言えません。
ご自身で確定申告を行う方でこの要件を満たすことが難しい場合には、税理士を上手に利用していただくと良いかもしれませんね。
申告期限内に申告書を提出すること
期限は守ることが特典を受ける要件です。
青色申告者のうち、現金主義による所得計算を選択していないこと
前々年分の不動産所得+事業所得の合計額が300万円以下の場合には、届出書を提出することによって現金主義により所得計算を行うことができます。
ここでの“現金主義”とは、収入金額や必要経費を実際に入金または出金した金額で計算することです。
■例 2021/12/30 売上100(未入金)、経費50(未払)
2022/ 1/15 入金100、支払50
・現金主義
2021年 収入0、経費0
2022年 収入100、経費50
・発生主義
2021年 収入100、経費50
2022年 収入0、経費0
上記例のように発生主義によらず、実際の入出金に合わせて集計するため、会計処理をより簡便に行うことができます。
ただし、この特例を使用している場合には、65万円の青色申告特別控除を受けることはできない、ということですね。
65万円の控除を受けたい場合には、現金主義ではなく発生主義による記帳を行いましょう。
次のいずれかを満たすこと
・その年分の確定申告を期限内にe-taxで行なっている
・その年分の事業に係る仕訳及び総勘定元帳につき、電子帳保存法の規定に従って電磁的記録の備付け及び保存を行なっている
上記のいずれかでOKです。
手っ取り早いのは、紙ではなくe-taxを使用して確定申告を行うことで要件を満たすことができます。
以上が満たすべき要件です。
正規の簿記の原則に従い貸借対照表を添付、こちらさえ達成できれば控除を受けられそうな気がしませんか?
まとめ
青色申告特別控除のうち、65万円の控除を受けるための要件について確認してみました。
10万円の控除が適用されている方の中に、貸借対照表の添付以外の要件は満たしているにも関わらず、
「手間だから」「面倒だから」「よく分からないから」etc
の理由で65万円の控除の適用を諦めていらっしゃる方を何名も見ています。
あと1つ要件を満たすだけで適用を受けられる、と考えてみると、挑戦してみる価値はあると思いますよ。
所得控除が55万円増えるとすると、
(仮に所得税率を10%とする)
55万円×(所得税10%+住民税10%+国保約10%)=16.5万円
の控除を得ることができ、合わせて金融機関に対して有用な決算書を手にすることができますので、ぜひ。