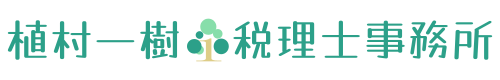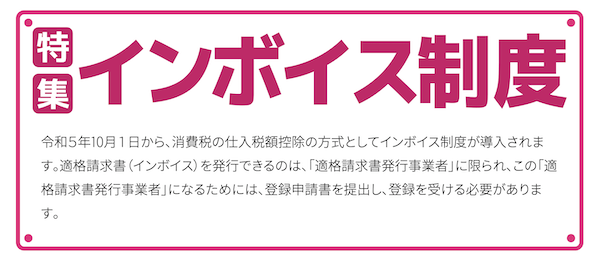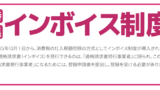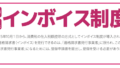令和3年10月1日より、消費税のインボイス制度に係る適格請求書発行事業者の登録申請受付が始まります。
そこで、インボイス制度のおさらい、第2回です。
1.仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書等の保存が必要となります。
2.請求書に記載する事項が変わります。
3.適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
4.登録を受けるためには申請が必要です。
5.登録を受けた事業者には、適格請求書を交付する義務が生じます。
6.税額計算の方法が変わります。
本日は「1.仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書等の保存が必要」です。
仕入税額控除を受けるための書類の保存要件
前回の記事の通り、
適格請求書等保存方式とは、
「事業者が納める消費税額を計算する時に引くことができる仕入税額ついての方式」
でした。
この仕入税額分の控除を受けるための要件が、令和5年10月1日より変更となります。
これまでの方式(区分記載請求書等保存方式)と、令和5年10月1日以降の適格請求書等保存方式での要件の違いはこちら。

仕入税額控除を受けるために保存しなければならない請求書は適格請求書等でなければなりません。
買い手となる事業者が適格請求書発行事業者以外の取引先から仕入を行った場合、適格請求書が発行されないため、その仕入に係る消費税については仕入税額控除の適用を受けることができなくなります。
保存の対象となる適格請求書等とは、
- 売り手が交付する適格請求書または適格簡易請求書
- 買い手が作成する仕入明細書等
(適格請求書の記載事項が記載されており、相手型の確認を受けたものに限る) - 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類
- 農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類
- 上記に係る電磁的記録
が該当します。
なお、次の取引は請求書等を受取ることが難しいため、帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができます。
- 公共交通機関による旅客の運送(3万円未満のもの)
- 自動販売機・自動サービス機からの商品の購入(3万円未満のもの)
- 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
- 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等で、使用の際に回収される取引
- 古物営業を営む者が行う適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)
- 質屋を営む者が行う適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)
- 宅地建物取引業を営む者が行う適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)
- 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)
- 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当)
保存要件以外で現在の方式と大きく変わる点が2つ
保存書類が適格請求書であることの他、現行制度から次の2点が変更となります。
①請求書がない場合の仕入税額控除の適用について
現行方式では「3万円未満の課税仕入れ」「請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるとき」は、一定の事項を記載した帳簿の保存のみ(書類の保存不要)で仕入税額控除が認められています。
適格請求書等保存方式への変更後は、この規定は廃止されます。
書類保存の対象となる取引について仕入税額控除を受ける場合には、必ず書類の保存を行うことが必要です。
②必要事項が記載されていない請求書等への追記は不可
現行方式では、仕入先から交付された請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の記載がないときは、これらの項目に限り、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追記することができます。
適格請求書等保存方式への変更後は、このような追記はできません。
仕入税額控除を受けるためには、適格請求書としての要件を満たした請求書等の交付を受けなければなりません。
まとめ
適格請求書等保存方式での仕入税額控除を受けるための要件を見てゆきました。
仕入税額控除のルールが変わる → (買い手が)適格請求書を受取ることが必要となる → (売り手が)適格請求書を発行する必要がある
という物事のつながりです。
次回は売り手側、発行しなければならない「適格請求書」がどのようなものか、見てゆきましょう。
【明日に向けて】
税理士業務のほか、いくつかタスクあり。
メリハリをつけてこなしてゆきます。